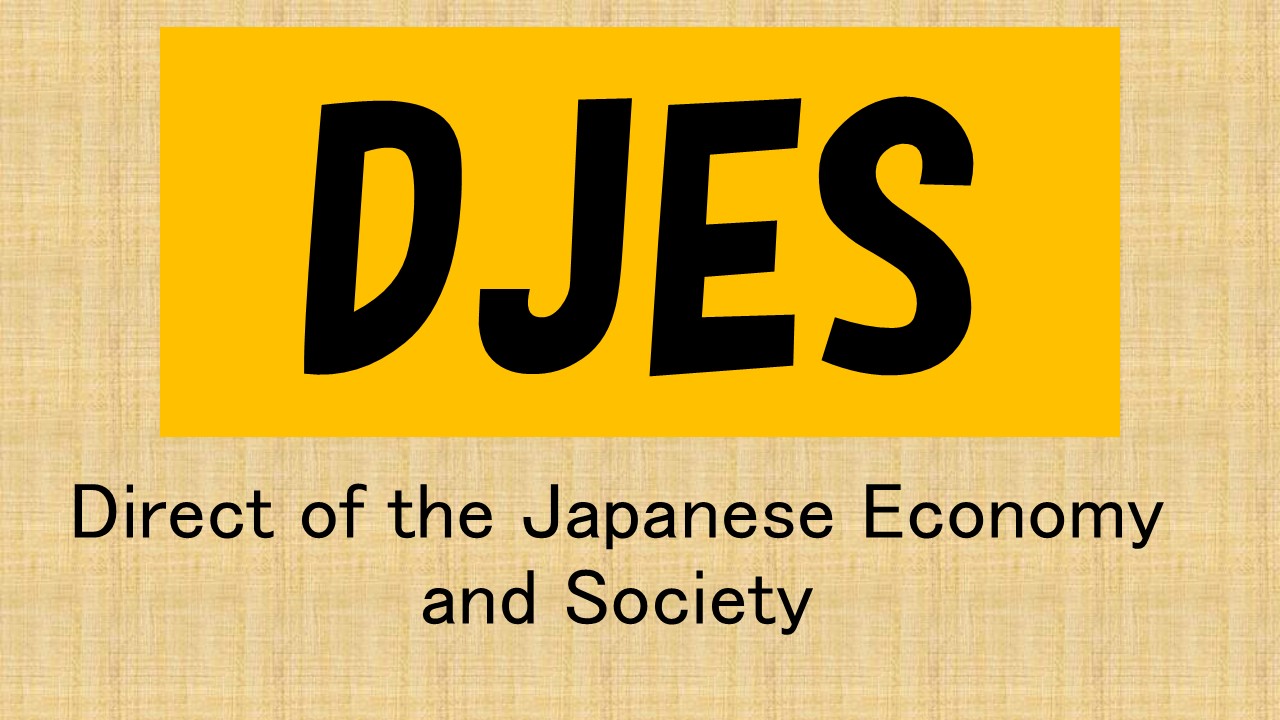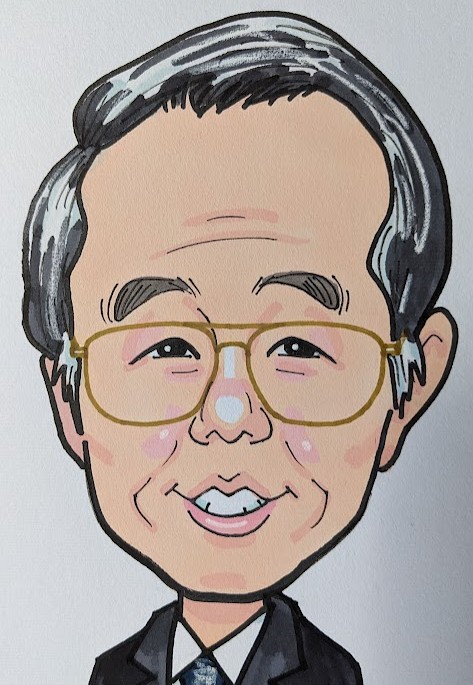戦後80年の日本経済を振り返ると、政府は経済成長率を高めるために様々な経済政策を展開してきました。このときの経済政策は、経済成長を主導するものとして民間設備投資と輸出の拡大を促進することに主眼がおかれました。特に民間設備投資が停滞した時、輸出主導の経済成長で日本経済の停滞を脱却しようという取り組みが強化されました。
輸出主導の経済成長で、主役的役割を果たしたのは、自動車や電気機械製品などを製造する機械組立産業でした。これらの産業は国際競争力が高く、基幹輸出産業を形成し、経済成長を牽引してきました。しかし、サプライチェーンがますますグローバル化するなかで、これまでどおり基幹輸出産業として引き続き国際競争力を維持し、経済成長の牽引役を果たすことができるのでしょうか。今回の投稿では、日本の機械組立産業に輸出主導の経済成長を牽引するだけの力が残っているかどうかを考察します。
考察の前提として、そもそも「輸出主導の経済成長」とは何かを説明します。
例えば、輸送用機械産業で生産する自動車への新規需要が1単位(=「1単位」は10億円分とか100億円分など任意に設定できる)発生した場合、輸送用機械産業の生産そのものが新規需要1単位分だけ増加します(これを「直接効果」と呼ぶ)。この時、輸送用機械産業の生産活動で用いられる原材料の投入の増加が必要になります。原材料の投入増加は、原材料の生産に関連する産業の生産増に波及します(これを「第1次間接効果」と呼ぶ)。原材料関連産業の生産増は、それに必要な 原材料の生産増をさらにもたらし、関連産業に生産増加が波及します(これを「第2次間接効果」と呼ぶ)。
「新規需要1単位の発生」は需要の増分と解釈できます。自動車の需要が前年より今年増加したとすると、その増分に対応して、関連する産業で、生産波及効果がなくなるまで国内生産額が増加します。各産業で増加した国内生産額から生産活動に要した原材料費の増加分を差し引くと各産業のGDP(=国内総生産)の増分がもとまります。各産業のGDP増分を集計すると国民経済レベルのGDP増分がもとまり、これを前年のGDPで割ると、自動車の需要増分が国民経済レベルの経済成長率に与えた影響を知ることができます。このように、財貨・サービスなどに需要増が生まれると、それが生産波及効果をもたらして国民経済レベルの経済成長率に影響をあたえることになります。
ここで需要は内需と外需に区分されます。内需は消費と投資で構成され、消費や投資が増加すると需要が増加することになります。外需は、自動車を事例にすると、海外からの需要である輸出ということになります。ところが、自動車は海外からも輸入されており、輸入される分だけ国産自動車の需要が減少することになります。したがって、外需は輸出から輸入を差し引いてもとまることになります。輸出から輸入を差し引いたものを一般的に「輸出超過」と言います。
したがって、財貨・サービスの輸出超過の増分が大きくて、これが経済成長率に大いに寄与するような状況が生まれた場合、これを「輸出主導の経済成長」と呼ぶことになります。
尚、今年の輸出超過が前年の輸出超過を下回る場合、輸出超過は減少し、その減少分だけ経済成長率を引き下げることになります。輸出超過の増減が経済成長率に影響を与えることに留意して下さい。
表1は、産業連関表をもとに、2005年、2011年、2015年、2020年の産業別輸出(2015年価格で評価した実質値)のデータをもとに、輸出の多い「ベスト8」を抽出しています。そのうえで、「ベスト8」産業の輸出超過をまとめています。ここでのデータは実質値ですから、輸出額という金額ベースではなく、輸出量という数量ベースに類似します。尚、以下で「輸出」という場合、基本的に実質値を示しています。
表1によると、輸出総計は、75兆4120億円(2005年)、81兆6100億円(2011年)、86兆7690億円(2015年)と着実に増加していますが、2020年はコロナの影響があって79兆5990億円に減少しています。
表1は、2005年の段階で輸出が多い上位8産業を示しています。第1位は輸送用機械の輸出でダントツに多く、17兆2340億円にのぼっています。第2位は、はん用・生産用・業務用機械が10兆5180億円になっています。第6位に電気機械が入り4兆7080億円です。これら3つの産業が「組立機械産業」の主要部分を構成し、組立機械産業だけで、日本の輸出の約43%占めており、基幹輸出産業であることは明らかです。組立機械産業の今後の動向が輸出主導の経済成長の可能性に大きく影響します。
組立機械産業の輸出の変化にはどのような特徴があるでしょうか。
輸送用機械の輸出は、2005年の17兆2340億円から17兆8150億円(2011年)、18兆4720億円(2015年)と増加傾向を示しましたが、2020年には15兆2770億円と大幅に減少しています。
輸出超過は、2005年に13兆7380億円で、2011年は14兆5560億円と増加しましたが、その後減少に転じ、13兆8830億円(2011年)、11兆4530億円(2020年)となっている。
輸出超過の減少傾向は、EVを軸とする中国の追い上げなど自動車をめぐる国際競争の激化を反映していると思われます。輸出超過は、2005年から2011年にかけては増加していますから、この間の経済成長率にはプラスに寄与しています。しかし、2011年から2015年、2015年から2020年ではいずれも輸出超過が減少していますから、経済成長率にはマイナスに働いたと言えます。今後輸送用機械の輸出超過が増加する見通しはあまりないので、輸送用機械が経済成長を牽引するという状況を期待するのは難しいと思われます。
はん用・生産用・業務用機械の輸出をみると、2005年の10兆5180億円から2011年に12兆4510億円と増加していますが、その後は11兆8460億円(2015年)、11兆6900億円(2020年)と推移し、明確な上昇傾向はありません。これまで日本の独断場であったこの分野で中国などの追い上げなどによって、国際競争の渦に巻き込まれており、輸出を継続的に増加させていくことは難しい状況です。
輸出超過は、2005年に6兆170億円から、2011年は7兆6700億円と増加していますが、その後減少傾向に転じ、6兆1720億円(2011年)、5兆5270億円(2020年)となっています。輸出超過が増加に転じることは至難のわざであり、はん用・生産用・業務用機械の輸出が経済成長を牽引することはあり得ないというのが現実です。
電気機械についても輸出超過をみると、1兆6270億円(2005年)、1兆2040億円(2011年)、1兆4510億円(2015年)、1兆330億円(2020年)と明らかな増加傾向を示していません。
組立機械産業は国際競争力が弱くなり衰退の道を歩んでいるわけではありません。厳しい経営環境の中で必死に踏ん張っている状況にあり、輸出超過を一定水準に維持し、経済成長の下支えの役を果たすことは十分可能であると思われます。但し、輸出超過の増加傾向を維持し、それが経済波及効果を通じて経済成長を高めるという輸出主導の経済成長を形成するとは考えにくい状況にあると言えるでしょう。