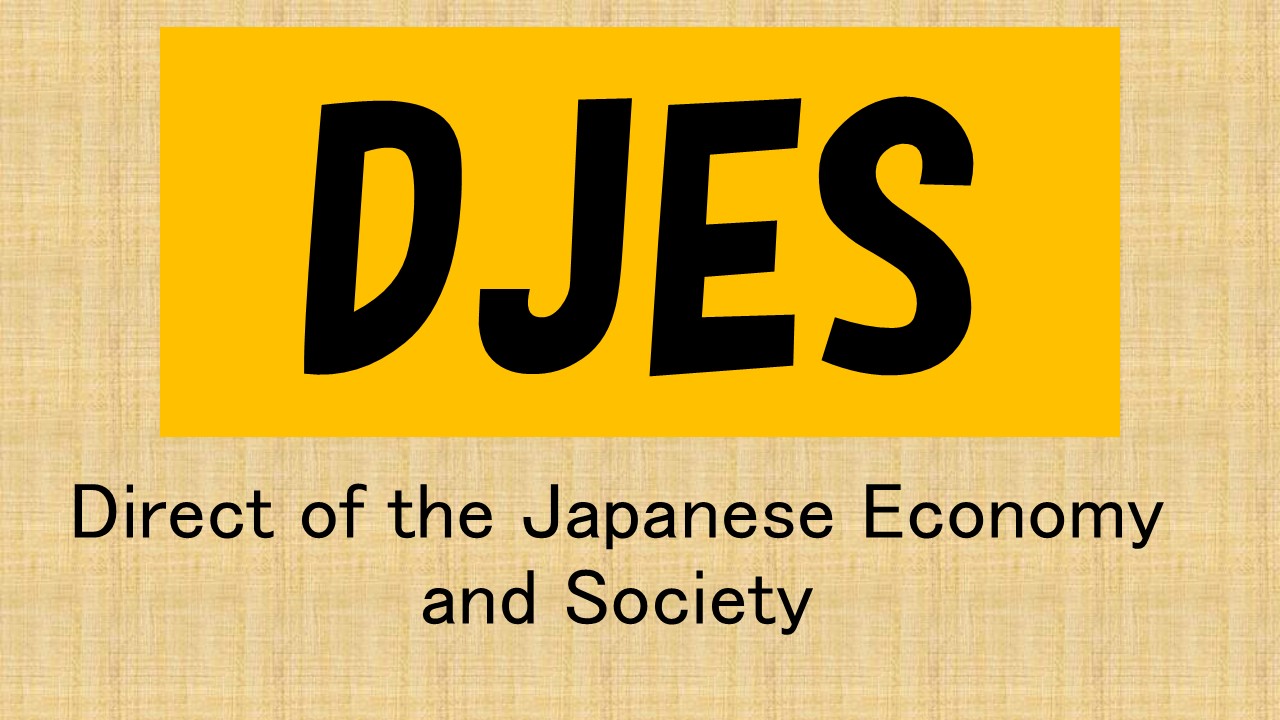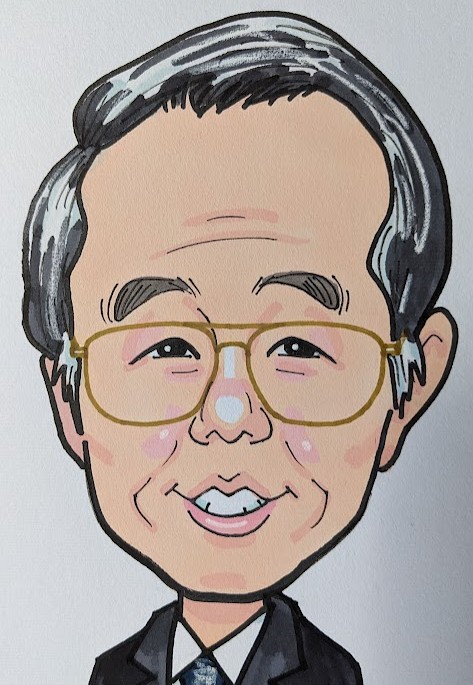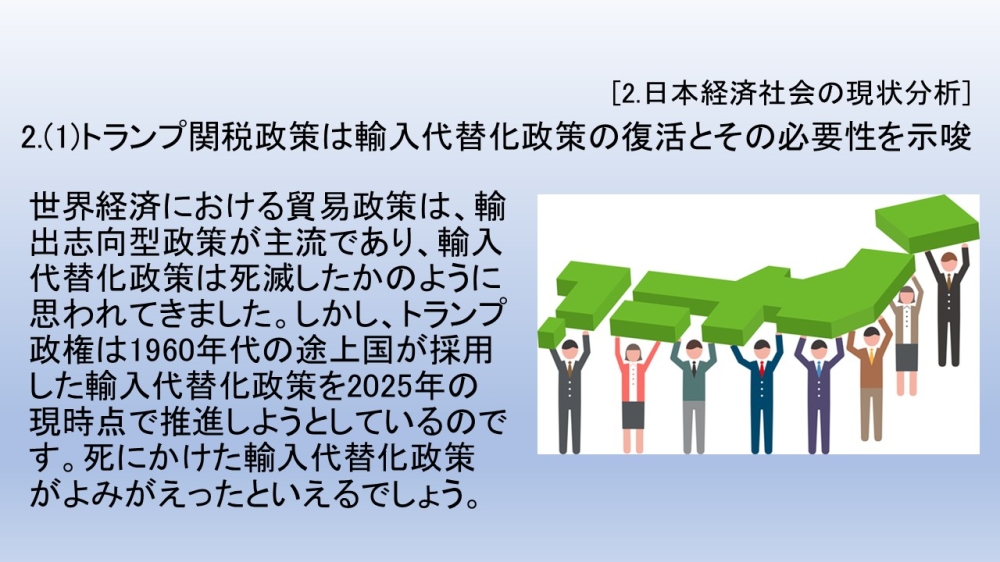
過激なトランプ関税政策で世界経済は混乱し、各国は対応策について右往左往しており、日本も例外ではありません。日本の場合特に、対米輸出で大きなウエイトを占める自動車への関税がどうなるかが大きな問題となっています。
1980年代後半の日米貿易摩擦の中心は自動車等の集中豪雨的対米輸出でしたが、2025年に入り、ふたたび自動車をめぐる貿易摩擦が再燃しているとみなすことができます。1980年代後半の日米貿易摩擦は結局トヨタなどの日系自動車企業が対米輸出を減らすために、アメリカでの現地生産に切り替えるということで決着しました。日米貿易摩擦を契機に自動車企業のみならずの多くの大企業の多国籍化が本格化し、国内では「産業の空洞化」問題をめぐって多くの議論が展開されました。
その後、アメリカにおける日本製自動車への需要は、特に品質の良い小型車を中心にますます増加し、現地生産だけでは供給が追いつかないので、日本からの対米輸出が再び増え始めました。長年にわたり、自動車産業の輸出増は日本の輸出増を牽引し、GDPを支える大きな役割を果たしてきました。
アメリカにしてみると、現地生産は定着したにも関わらず、日本からの自動車輸入が再び増え続けたことに強い不満があり、それを背景に自動車を中心に過激な関税政策の実行可能性を日本につきつけているのです。
自動車を中心とする第2の日米貿易摩擦にどう対応したらいいのでしょうか。日本政府は自動車への関税率引き上げを断念させ、何とか現在の自動車輸出数量を維持したいと考えています。そのために、取引の材料としては、農産物・液化天然ガス(LNG)・防衛装備などの輸入拡大、非関税障壁の撤廃、自動車輸出台数の自主規制などを検討課題にしようとしています。
しかしこれらの取引で、自動車の対米輸出が今後とも増加し続けるであろうというアメリカの懸念を払しょくするのは至難の業です。結局のところ、自動車業界自らが対米輸出を減らし、現地生産をふやすという選択をせざるをえないと予想されます。
トランプ政権が、アメリカの製造業の復活を標榜する時、そのコアは自動車産業にあります。国籍は問わないが、国内の自動車産業への設備投資が増加し生産体制が拡大すれば製鉄産業などへの波及効果も大きく、製造業全体への復活に結び付くと考えているようです。アメリカ国内への直接投資拡大要求こそトランプ政権の真骨頂であり、日本の自動車産業はいずれかの段階でその要求を飲まざるをえないでしょう。
アメリカは、戦後の自由貿易体制の旗振り役でしたが、今や国益を盾に自由貿易に歯止めをかけ、自由貿易を前提に多くの国が採用してきた輸出志向型政策に待ったをかけようとしています。アメリカ自身は輸入代替化政策を重視する立場に転換しました。トランプ関税政策の本質は、輸入代替化政策を貿易政策の柱にすえた点にあるといえるでしょう。
そもそも輸入代替化政策とは何でしょうか。戦後多くの発展途上国は、列強国の植民地支配から解放され民族的独立を勝ち取りました。独立前の途上国は、多くの財供給を列強国に依存しており、輸入超過が慢性化していました。国内の基幹産業を戦略的にも一刻も早く振興し、これまで列強国に依存してきた財供給を国産化して経済的自立の基盤を確立することが焦眉の課題となっていました。
国産化するということは、これまでの輸入という形の供給から、国内生産という供給に転換していくことでした。そのためにとられた成長政策が、特に工業製品に照準をおいた輸入代替化政策です。輸入代替化政策とはこれまで輸入していた工業製品を国産に置き替えていくことを目的とした産業振興政策でした。
多くの独立途上国が採用した輸入代替化政策は失敗しました。輸入代替化政策は国内の生産基盤確立を優先した供給サイドの政策でした。生産基盤を確立して生産拡大をめざしたが、残念ながら国内市場はまだ発展していなかったので需要が増えず、過剰生産の状況から脱却することができず、企業活動は不振に陥り、基幹産業の育成は成功しませんでした。多くの途上国は国としての独立は勝ち取りましたが、経済成長率を高める軌道に乗ることはできず、長期の経済停滞が続き、人々の生活向上は遅々として進みませんでした。輸入代替化政策は失敗であったというのが多くの国の共通認識であったと言えるでしょう。
輸入代替化政策にかわって、輸出促進を重視した輸出志向型政策を推進し、輸出を増やしその供給体制を拡大するために設備投資拡大を誘引し、内需拡大をめざしました。輸出志向型政策は輸出と設備投資を両輪としながら経済成長を高めようというものでした。
輸出志向型政策は途上国のみならず先進国にとっても有効であり、輸出志向型政策の採用によって、世界経済は戦前にはみられなかったような活性化の道を歩み始めました。輸出が活性化するためには、関税や非関税障壁を取り除き自由貿易体制を確立して財・サービスの円滑な取引を促進することが不可欠になりました。
世界経済における貿易政策は、輸出志向型政策が主流であり、輸入代替化政策は死滅したかのように思われてきました。しかし、アメリカは1960年代の途上国が採用した輸入代替化政策を2025年の現時点で推進しようとしているのです。死にかけた輸入代替化政策がよみがえったといえるでしょう。
このようなアメリカの動きをみると、中長期的にみた場合、これまでのような自由貿易体制一辺倒の世界経済は修正せざるをえないと思われます。これから先、どの国も大企業を中心に多国籍化し、企業は国境を越えてますます生産活動を展開するのはほぼ確実です。この時、多国籍企業が生産拠点を強化する国では雇用の維持拡大ができ、経済成長も保証されるかもしれません。しかし、多国籍企業の生産拠点が希薄な国では製造業などの停滞が予想され、アメリカはその典型でした。国籍を問わず多くの多国籍企業がアメリカ国内で製造業の生産拠点を強化し、輸入を国内生産に転換するという輸入代替化政策をアメリカが展開しようとするのは一定の合理性があります。
しかし、アメリカが輸入代替化政策を推進すれば、日系自動車企業では対米直接投資を促進しアメリカでの生産拠点を拡大することが不可避になり、それを前提にすると対米自動車輸出減少が貿易収支の悪化を招き、日本経済が低経済成長からなかなか脱却できないという「蟻地獄」に陥る可能性があります。
したがって、自動車輸出が減少したとき、どこで輸出を増やすかを検討する必要があります。インバウンド関連産業やアニメ産業など第3次産業で有望な輸出産業が成長するかもしれませんが、製造業では国際競争力は激しく、国内を生産基盤とする新たな輸出産業を育成するのはなかなか難しい状況があります。
そこで、貿易収支の悪化に歯止めをかけるために、日本も輸入代替化政策を導入し、自由貿易体制を部分的に修正していく必要があるでしょう。日本の輸入の大半は原油などです。原油の輸入を減らことができれば、付加価値がその分国内にとどまり、GDPが増加します。原油は電力などのエネルギー産業と深く関わるので、自然エネルギーなどへの設備投資をふやし生産体制を抜本的に増やせば、それが原油の輸入を減らし輸入代替化を実現することになります。あるいは、農産物の生産基盤を再構築する設備投資を増やし生産を抜本的に増加させ自給率を上昇させれば、輸入代替が進みGDP増加に寄与します。
アメリカが対内直接投資を増やし現地生産を強化して輸入を国内生産に代替するという政策を持続的に推進する場合、日本は原油や農産物などの輸入代替化によってGDPを増やすために、自然エネルギーを中心とするエネルギー供給や農産物の国内生産基盤の拡大の設備投資を活性化させる政策が重要になります。