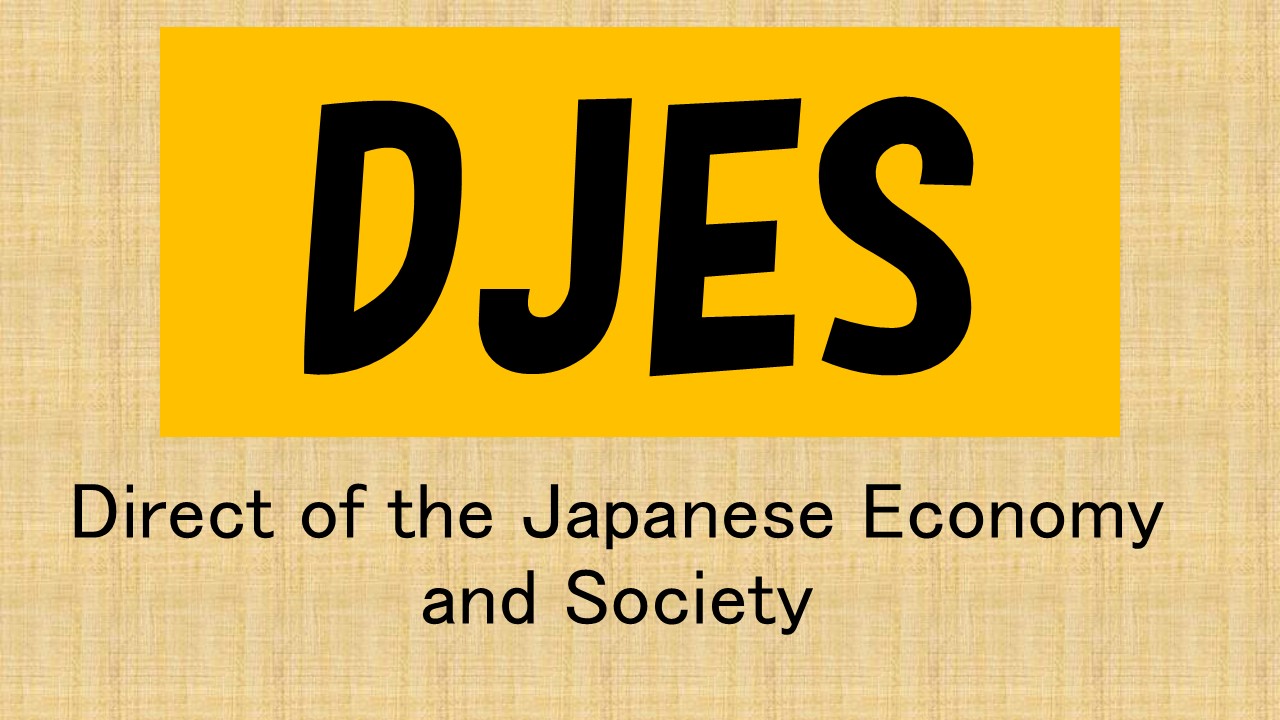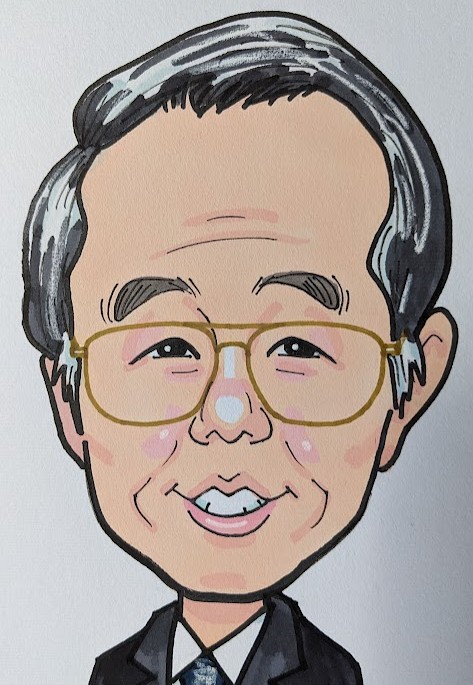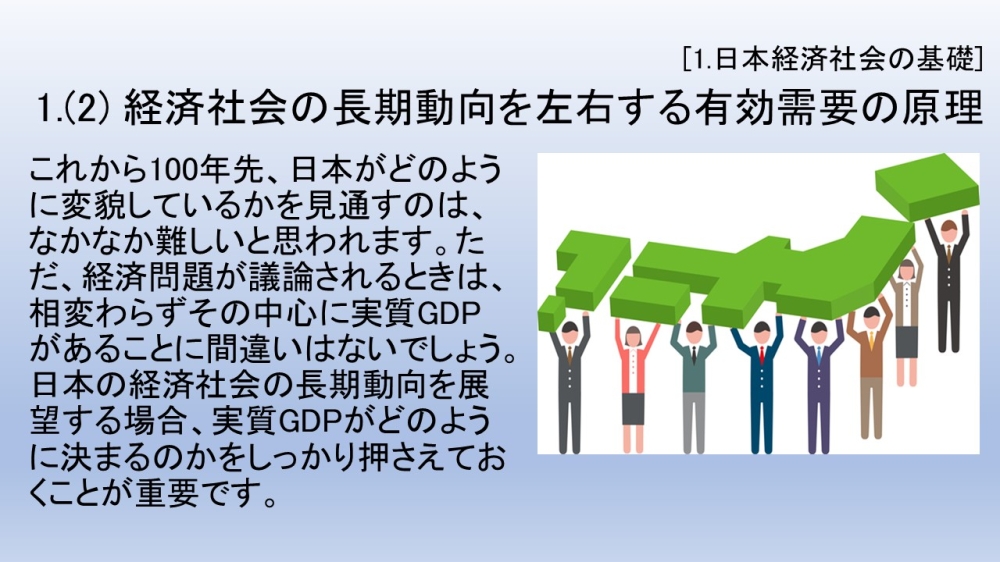
これから100年先、日本がどのように変貌しているかを見通すのは、なかなか難しいことだと思われます。ただ、経済問題が議論されるときは、相変わらずその中心に実質GDPがあることに間違いはないでしょう。実質GDPを無視した経済行動や経済政策などが実施されているとは想像もできないことです。
過去・現在・未来において、経済活動のもっとも重要な経済変数は実質GDPであり続けるでしょう。ですから、日本の経済社会の長期動向を展望する場合、実質GDPがどのように決まるのかをしっかり押さえておくことが重要です。
実質GDPがどのように決まるかについての考え方には、さまざまな議論があります。しかし、やはり、「需要が供給を規定する」というケインズの「有効需要の原理」が、シンプルで説得力のある考え方ではないでしょうか。
有効需要は、財・サービスを購入したいという単なる願望ではなく、貨幣的支出によって実現される現実の需要です。需要が供給を規定するという「有効需要の原理」は、有効需要の大きさが、実質GDPなどの経済活動の水準(=供給)を決めると言い換えることができます。したがって、この考え方によると、有効需要の大きさが実質GDPを決めるということになります。(尚、以下では、有効需要を単に「需要」と呼ぶことにします。)
1991年のバブル経済崩壊後、日本経済は「失われた20年」とか「失われた30年」とか言われてきましたが、長期停滞の主要な要因は、需要が不足したことに起因しています。戦後日本経済が高度成長を実現したのは需要が旺盛であったからです。まさに、日本の経済成長の変容は、ケインズがいうところの、需要が実質GDPを規定した変容であったといえるでしょう。
需要が実質GDPを規定するという有効需要の原理の重要性はわかったとして、次に問題になるのは、そもそも需要はどのように決まるのかということです。別の言い方をすると、需要はどのようにつくりだされていくのかという需要創出のプロセスを理解することが必要になります。次回では、需要創出のプロセスについて議論します。