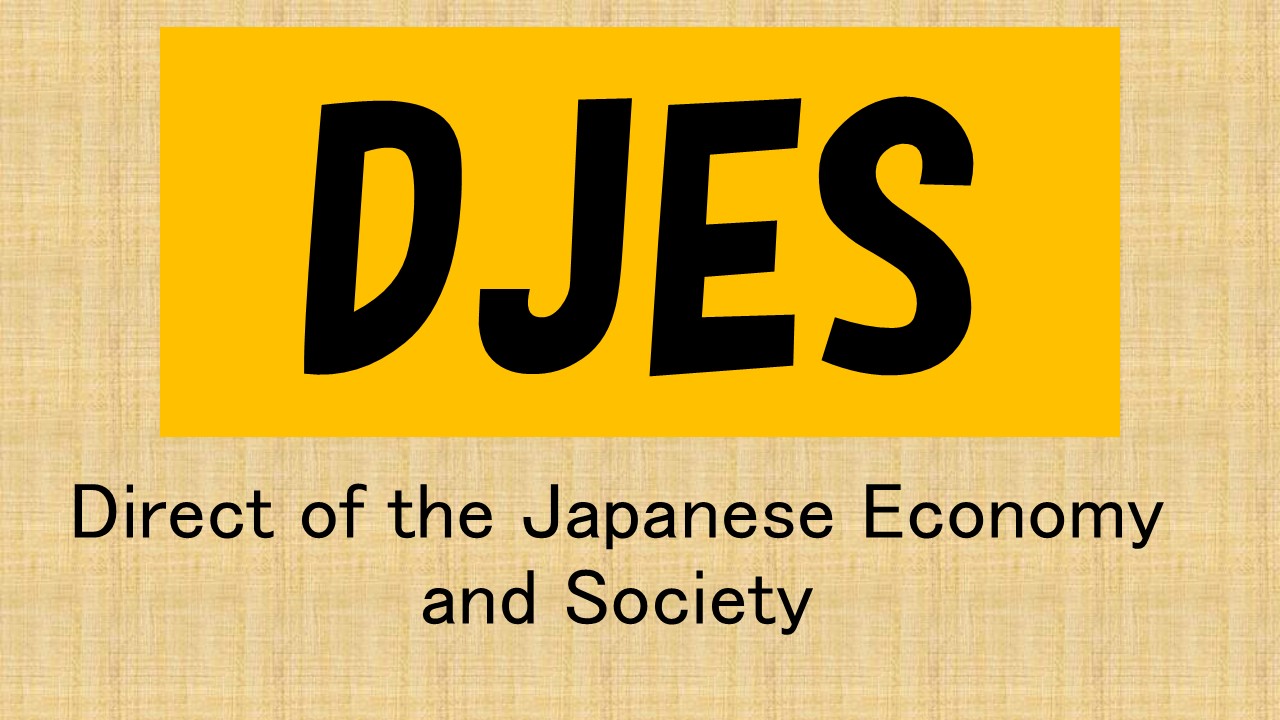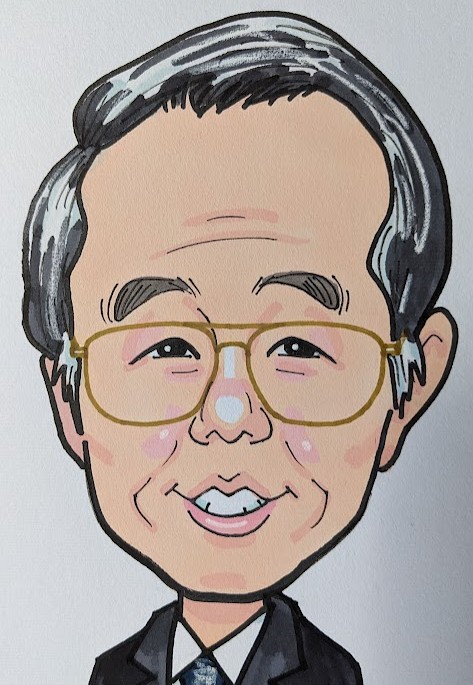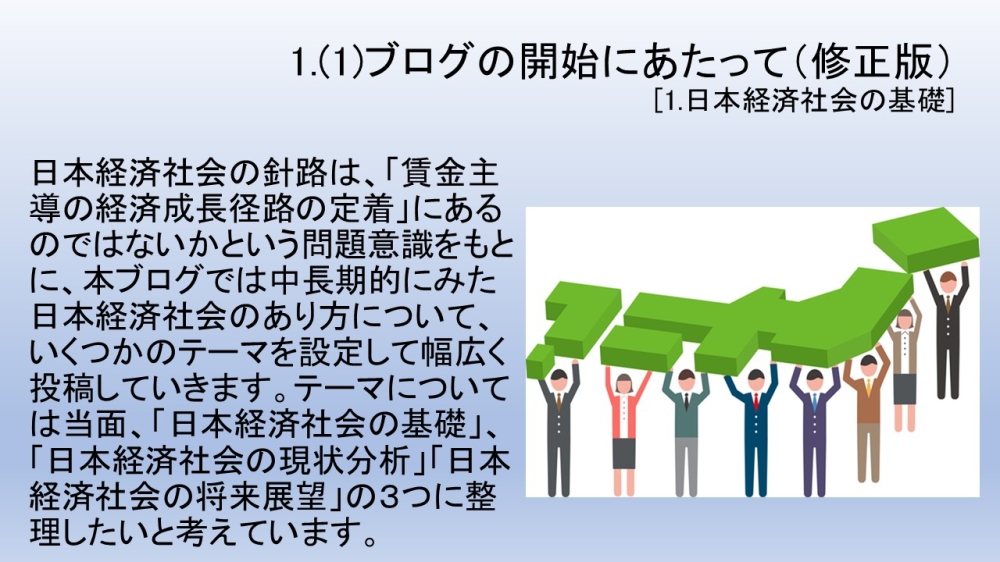
戦後日本経済は経済成長率を重視して経済社会が形成されてきました。経済成長率重視とは、投資と輸出が経済成長の牽引役を担い、その牽引力を強化するために様々な経済政策を展開するというものでした。経済成長率が高まれば、付加価値が増加するので賃上げが実現して家計の生活水準も向上し、政府は多くの税収をえることができ、それをもとに社会保障の原資も確保することができました。
しかし、1991年のバブル経済崩壊後、投資のうち民間投資(=民間企業設備投資+民間住宅投資)及び輸出ともに増加率が鈍りはじめ、経済成長率が大幅に低下しました。その状況を改善するため、政府は公共投資を拡大しましたが、経済成長率低下に歯止めをかけることができず、副作用として多額の財政赤字が累積し、財政赤字問題が経済成長を阻害する大きな重石になってしまいました。経済成長率の低下とともに、家計に分配される付加価値の増加率も鈍化し、賃上げなどによる家計の生活水準向上も大きく制約される状況が現在まで続いています。このままでいくと、「失われた20年」が「失われた30年」、さらには「失われた40年」になりかねない状況です。
このような中で、経団連は、「日本産業の再飛躍へ~長期戦略にもとづく産業基盤強化を求める~」(2024年4月16日)という政策提言をもとに、経団連会長は、国内の民間の設備投資額を2040年には現在の2倍の200兆円まで伸ばすという目標を示し、官民一体の取り組みの重要性を強調しました(NHK 2025年1月27日)。
これは、戦後日本経済が実現した「高度経済成長よ、もう一度」という発想に近いと思われ、民間設備投資主導の経済成長をめざすというものです。2024年から2040年にかけて、年増加率に換算すると約4.5%で持続的に拡大すると想定していることになります。
民間設備投資は、「将来予想される総需要の変化率」を示す期待成長率に大きく影響を受けます。経団連は、生成AIに代表されるイノベーションが期待成長率を高めると想定しています。イノベーションが期待成長率に与える影響は一定あると思われますが、期待成長率に大きく影響を与えるのはいうまでもなく将来の総需要のゆくえです。将来の総需要が持続的に増加することに企業が確信を持てば、期待成長率も高まり、民間設備投資が持続的に拡大する可能性があります。将来の総需要の持続的拡大をどう実現するかという視点について、経団連の発想は従来型の延長と言わざるをえません。
他方、もっと家計消費を重視した経済成長を追求すべきではないかという議論が盛んに行われるようになりました。具体的には持続的賃上げを実現して、経済成長の牽引役を民間設備投資や輸出などから賃金に転換させ、賃金主導の経済成長径路を定着させていくという発想です。
賃金は個別企業にとっては人件費というコストですから、賃上げすればその分もうけが少なくなります。賃上げは一時的にはもうけを減少させますが、他方、賃上げによって消費拡大がおこり、総需要が増加し、売上が増加して、儲けをとりもどすことができます。このような賃上げの二重の経済効果について企業が共通認識をもつことができれば、賃上げによる消費主導の持続的総需要拡大が期待成長率を高め、民間設備投資拡大を引き出し、経済成長を高める可能性があります。
日本経済社会の針路は、「賃金主導の経済成長径路の定着」にあるのではないかという問題意識をもとに、本ブログでは中長期的にみた日本経済社会のあり方について、いくつかのテーマを設定して幅広く投稿していきます。
テーマについては当面、「日本経済社会の基礎」、「日本経済社会の現状分析」、「日本経済社会の将来展望」の3つに整理したいと考えています。
これからの日本経済社会のあり方を考える場合、具体的な数値データを根拠に議論することが説得的だと思います。そこで日本経済社会のコアの部分をとりだしてモデルを作成し、シミュレーションするという分析手法を重視します。そのために、「日本経済社会の基礎」をテーマとして、コアとなる日本経済社会の構造を解説します。
「日本経済社会の将来展望」では、主に産業連関表とSNA統計データをもとに投稿者が作成した中長期展望モデルを紹介します。そのうえで、いくつかのシナリオをもとにシミュレーションした将来経済社会像を数値的に表現し、「賃金主導の経済成長径路の定着」の可能性を論じます。
モデル・シミュレーションを通じて、将来経済社会を展望するためには、どうしても前提条件が必要です。ここでは、現状分析をもとに多面的に日本経済社会の将来動向と政策課題を明らかにして、前提条件を設定します。「日本経済社会の現状分析」は、前提条件を準備するためのテーマと位置付けていいます。
日本経済社会の動向は、「家計」、「企業」、「政府」及び「海外部門」という4つの経済主体の経済行動に大きく左右されることになります。そこで、投稿するテーマが主にどの経済主体の動きを考察しているのかを明確にするために、「家計」、類似した財やサービスを生産する企業を統合した「産業」、中央政府・地方政府・社会保障基金から構成される「一般政府」、海外部門との関係を示す「国際経済」という4つのタグに分けて整理することにします。また、4つの経済主体の経済行動の総合的パフォーマンスを考察するテーマについては、「マクロ経済」というタグをつけることにします。